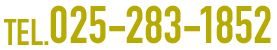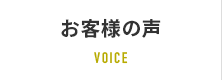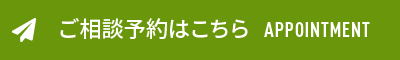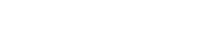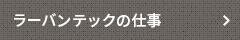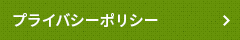新潟県上越市中部にある春日山をご存じだろうか。
戦国時代の名将、上杉謙信公の居城があった場所だ。先日、初めて山に登ってみた。
知り合いからは何もなくつまらない、良くも悪くも新潟っぽいのかもしれない等と聞いたことがあった。なかなか手厳しい。
標高は180m程で駐車場のある登り口には大きな案内板。春日山城は全国屈指の山城として伝わり、今も土塁や曲輪の形状が残っていたが直江、柿崎などの名前が記載された武将屋敷跡に心が躍る。時代は違えど同じ景色を見ている、天守跡から見える直江津の港、戦の前に籠られたという毘沙門堂。
一人だったので時間を気にしなすぎて少し寂しくなった。駐車場に戻ると、ご高齢のご夫婦とお孫さんが案内板を熱心に見上げていた。決して近いと言えない他県ナンバーの車もちらほら。
戦上手な名将は今も名を残しているが、裏切りが常の戦国で義を掲げた郷土の英雄が一段と誇らしく感じた。